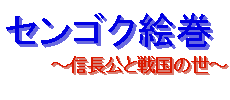
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< あ行 >>
あ い う え お
| ◆合印 【あいじるし】 戦場で敵味方の区別をつけるためにつけた印。 同じ襷(たすき)を使う、同じ字を服にいれるなど方法は様々。 |
| ◆足軽 【あしがる】 物頭に指揮される徒歩の雑兵。槍組、弓組、鉄砲組などがあった。 [ 関連 ] → 物頭 |
| ◆小豆坂七本槍 【あずきざかななほんやり】 織田信秀が今川勢と戦った「第一次小豆坂合戦」において活躍した織田家の武将。 織田信光、織田信房、佐々勝道、佐々孫介、中野重吉、下方貞清、岡田重能の七人のこと。 |
| ◆敦盛 【あつもり】 「人間五十年、下天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり。(人の一生はせいぜい50年。その50年も下天(六欲天の最下位)においては1日にしかあたらないのである。まことに夢幻のようなものだ。)一度生を得て、滅せぬもののあるべきか・・・」という、信長が好んだ一節が有名。 これは幸若舞の「敦盛」で、能の「敦盛」とはまた別である。ちなみに、敦盛とは源平時代の平清盛の甥の平敦盛のことで、一ノ谷合戦において16・7歳という若さで熊谷直実に討たれている。 |
| ◆一族 【いちぞく】 血縁や親族関係にある者。 |
| ◆一領具足 【いちりょうぐそく】 土佐の長曾我部氏に仕える半農半兵の身分の低い武士のこと。 平時の農耕作業にも一領(ひとそろい)の具足を常備していたことから、こう呼ばれた。 |
| ◆移封 【いふう】 豊臣秀吉・徳川家康ら天下人が行った、大名の領地を他の地域に移動させること。(=国替え・移封) [ 関連 ] → 国替え 転封 |
| ◆印判 【いんぱん】 現代でいう印鑑。正式な文書には署名と花押をいれるのが基本だが、略式として印鑑が使われた。 織田信長が使用した「天下布武」の印判が有名。 [ 関連 ] → 花押 |
| ◆馬揃え 【うまぞろえ】 各軍の訓練度などを検閲する閲兵式。織田信長は自軍の勢威を周囲に示す意味でも使用した。 軍事パレード。 |
| ◆馬廻 【うままわり】 馬上の大将の周囲を固め警護する役の騎馬の武士。 親衛隊のような者で、大将の子飼いの武将などで後に出世した者は馬廻出身が多い。 |
| ◆烏帽子 【えぼし】 成人した男子のかぶり物のこと。 [ 関連 ] → 烏帽子親 |
| ◆烏帽子親 【えぼしおや】 男子の元服の際に、仮親となり烏帽子をかぶせる人のこと。 [ 関連 ] → 烏帽子 |
| ◆大手 【おおて】 城の表門、正門のこと。または、敵の正面から攻めること。 [ 関連 ] → 搦手 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る