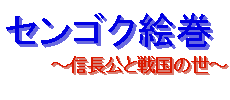
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< ま行 >>
ま み む め も
| ◆巻攻め 【まきぜめ】 敵城を包囲して兵糧を絶ち、兵の士気が落ちた所を謀略によって城を落とす攻め方。(=兵糧攻め) [ 関連 ] → 兵糧攻め |
| ◆まばらがけ 【まばらがけ】 将兵が各自自由気儘に敵と戦うこと。軍の統制を乱すという理由から禁止している家中が多かった。 (=面々かせぎ) [ 関連 ] → 面々かせぎ |
| ◆水攻め 【みずぜめ】 城の周囲に堤防を築き、そこに周囲の川から水を引いたり雨水を利用したりして、城を水没させる兵糧攻めの一種。 [ 関連 ] → 兵糧攻め |
| ◆面々かせぎ 【めんめんかせぎ】 戦場で将兵が各自自由に敵を討ち、戦功を立てること。軍の統制を乱すという理由から禁止している家中が多かった。(=まばらがけ) [ 関連 ] → まばらがけ |
| ◆申次 【もうしつぎ】 織田家の外交を担当する職。信長の信任を得て他家と交渉する役を担った。毛利家への申次だった羽柴秀吉のように、後に方面軍指揮官となった。 |
| ◆物頭 【ものがしら】 槍組、弓組、鉄砲組など徒歩の隊の隊長。足軽大将のこと。 [ 関連 ] → 足軽 |
| ◆物見 【ものみ】 斥候。戦場の地勢や敵方の動静、勢力、布陣などを探る役。情報の正確さが求められる重要な役のため、戦場慣れした者が選ばれた。 |
| ◆守役(=傅役) 【もりやく】 武将の子が一人前になるように、幼年期につけられる養育役・後見人のこと。 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る