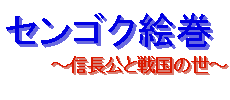
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< な行 >>
な に ぬ ね の
| ◆入道 【にゅうどう】 仏門に入った人や入ること。(≒出家・剃髪) [ 関連 ] → 出家 剃髪 |
| ◆年貢 【ねんぐ】 領民が領主に納めた税。金銭や田畑で取れた作物などを納めた。 |
| ◆信長記 【のぶながき】 小瀬甫庵(おぜほあん)著作の伝記文学書。豊臣秀次・堀尾吉晴に仕えたのち流浪の身となった儒医であった甫庵が儒教的理念宣揚のために英雄としての信長像を書いたもの。 そのため脚色された部分が多く歴史書としての価値は低い。しかし、桶狭間の奇襲戦や長篠の鉄砲3000挺による三段撃ちなど、有名な話が多い。成立は慶長9年から同15年(1604〜1610)頃と考えられている。 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る