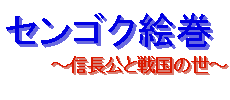
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< は行 >>
は ひ ふ へ ほ
| ◆陪臣 【ばいしん】 家来のその又 家来のこと。つまり、織田信長の家来の羽柴秀吉の家来の竹中半兵衛のような存在。 この場合、信長から見て半兵衛は陪臣となる。 [ 関連 ] → 直臣 |
| ◆婆娑羅 【ばさら】 見栄を張り、派手に振舞うこと。勝手気ままに狼藉を働くこと。綺羅をかざった服装、風俗。 |
| ◆旗頭 【はたがしら】 武士による集合体の大将のこと。室町幕府における守護は、その国の地頭を束ねる旗頭ともいえる。 [ 関連 ] → 守護 |
| ◆被官 【ひかん】 大名直属の武士や臣従した土豪たちのこと。 |
| ◆兵糧攻め 【ひょうろうぜめ】 敵城を包囲して兵糧を絶ち、兵の士気が落ちた所を謀略によって城を落とす攻め方。(=巻攻め) [ 関連 ] → 巻攻め 水攻め |
| ◆平首 【ひらくび】 身分の低い侍の首。 [ 関連 ] → 対面 首実検 検知 兜首 |
| ◆平攻め 【ひらぜめ】 策を弄せず、我武者羅に攻める攻め方。(=力攻め) [ 関連 ] → 力攻め |
| ◆譜代 【ふだい】 「譜」はつづくと読み、代々にわたって主に仕えた家臣を意味する。 江戸時代では、徳川家に代々仕える者を譜代。関ヶ原合戦後に仕える者を外様と称した。 |
| ◆筆本改め 【ふでもとあらため】 誓紙などの重要文書の署名・血判が、本当に当人によって行われたものかを検分すること。 [ 関連 ] → 誓紙 |
| ◆奉公構い 【ほうこうがまい】 豊臣秀吉が創った処罰の一種。自家から追放し、更に他家に仕えることをも禁じること。 |
| ◆本領安堵 【ほんりょうあんど】 領主が服従する際に、現在持っている領地を引き続き所有することを認めること。 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る