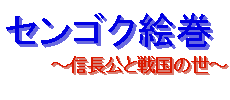
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< さ行 >>
さ し す せ そ
| ◆西国 【さいごく】 畿内以西の国のこと。 [ 関連 ] → 東国 |
| ◆仕置家老 【しおきかろう】 名家において主君を補佐し、家中を総括した最高位の家老のこと。 |
| ◆直臣 【じきしん】 直接の部下のこと。 [ 関連 ] → 陪臣 |
| ◆執権 【しっけん】 鎌倉幕府の実権を掌握した北条氏が有名だが、戦国大名家の中には重臣を執権と呼ぶこともあった。 |
| ◆守護 【しゅご】 鎌倉・室町幕府が地方の警備や治安維持にあたらせた職。戦国時代には名は意味を持たず、力ある守護は守護大名として存続したが、力のない守護は戦国大名に取って代わられた。 [ 関連 ] → 守護大名 戦国大名 |
| ◆守護代 【しゅごだい】 守護が広大な自領地を分割管理するために各地方に派遣していた、守護の代行を行う職。戦国時代には力をつけ、下克上によって守護に取って代わった守護代もあった。 [ 関連 ] → 守護 |
| ◆守護大名 【しゅごだいみょう】 幕府から派遣された任地で支配権を確立させ、領主となった守護のこと。 [ 関連 ] → 守護 大名 戦国大名 |
| ◆出家 【しゅっけ】 仏道の修行をするために僧になること。(≒剃髪・入道) [ 関連 ] → 剃髪 入道 |
| ◆庶子 【しょし】 側室など正室以外の女性から生まれた子のこと。 [ 関連 ] → 嫡子 猶子 |
| ◆殿 【しんがり】 軍を退く際に、最後方で敵の追撃を食い止める部隊のこと。全軍の撤退が終了するまで退けないため最も困難で死亡率の高い役割。語源は、後駆(しりがり)。 |
| ◆陣僧 【じんそう】 戦死者に念仏を唱え埋葬する従軍僧。平時には諸国を遊行し、諜報活動を行った。 |
| ◆信長公記 【しんちょうこうき】 尾張時代から信長の側近だった太田牛一が、自身の記録と他人から得た話を元に書いた信長の一代記。信長についての一級歴史史料として有名で後世に残るほとんどの逸話がこの本を元にしたものである。 慶長の初め頃から慶長15年(1610)にかけた書かれたようだが、一般の人の目に触れるようになったのは活字化された明治時代になってからである。 |
| ◆捨扶持 【すてぶち】 由諸ある家の老人・婦女子・廃疾者などの生活を助けるために与えられた給米。 |
| ◆誓紙 【せいし】 約定を記した文書や起請文。 |
| ◆戦国大名 【せんごくだいみょう】 戦国時代に各地に割拠し、一国から数カ国にわたって独自の支配体制を確立させていた大名。家臣団を編成し、城郭を中心として城下町を作り、独自の各種法律を制定して富国強兵に努めた。 ちなみに、戦国大名という言葉は、第二次世界大戦後に創作された学術用語。 戦国時代においては「戦国」や「大名」という言葉はあったが、戦国大名という言葉はなかった。 [ 関連 ] → 大名 守護大名 |
| ◆先鋒 【せんぽう】 (=先手・先陣) 戦場において自軍の先頭で働く人物や部隊のこと。 [ 関連 ] → 後詰 |
| ◆奏者 【そうしゃ】 主人への取り次ぎ役。拝謁の案内や上申事項の伝達役を行った。 |
| ◆惣領 【そうりょう】 武士団における一族の長。 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る