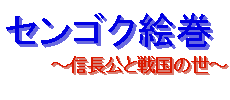
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< か行 >>
か き く け こ
| ◆改易 【かいえき】 処罰の一種。領地・禄高・役職を没収すること。 |
| ◆花押 【かおう】 天皇や公家、武将が用いた図案化されたサインのこと。(=書判) |
| ◆懸かり引き 【かかりびき】 直江兼続が長谷堂の戦いの撤退撃で見せた戦法。 繰り引きを進化させた戦法で、撤退時に鉄砲隊を伏せておき、追撃に来た敵兵に一斉射撃。 怯んだ所に反転攻勢をかけ、敵が下がった所で一斉に退却するというもの。 |
| ◆家宰 【かさい】 関東管領・上杉家では、家臣の中でももっとも重要な職務を家宰と称した。 |
| ◆金堀り攻め 【かなほりぜめ】 金堀衆(抗夫)を用いて、城外から城内までトンネルを掘らせて攻める攻め方。 |
| ◆加判家老 【かはんかろう】 大名の発給する文書に印判を加える役職の最高位の者のこと。 [ 関連 ] → 印判 |
| ◆兜首 【かぶとくび】 兜を付けた身分の高い武将の首。 [ 関連 ] → 対面 首実検 検知 平首 |
| ◆搦手 【からめて】 城の裏門のこと。または、敵の背後から攻めること。 [ 関連 ] → 大手 |
| ◆家老 【かろう】 重臣の中でもトップクラスの者。一族・重臣の中でも、優秀な者、家格が高い者が選ばれた。 |
| ◆貫高 【かんだか】 土地の石高を銭貨に換算したもの。基本的に1石=1貫だが、地域によって多少の差はあった。 ちなみに1貫を現代の値段に換算すると、諸説あるが約25万円ほどになるらしい。 [ 関連 ] → 石高 |
| ◆関八州 【かんはっしゅう】 関東八ヶ国の総称。八ヶ国とは、相模(神奈川)、武蔵(東京・埼玉)、上野(群馬)、下野(栃木)、安房(千葉)、上総(千葉)、下総(千葉)、常陸(茨城)のこと。 |
| ◆官符衆徒 【かんふしゅと】 本来は平安時代以後に大寺院に居住して学問・修行の他に寺内の運営実務にあたった僧侶のこと。 興福寺が守護の大和国では、自国の武士を衆徒としたため、大和武士を指す場合もある。 |
| ◆管領 【かんれい】 室町幕府において将軍の補佐役にあたる役職。その権限は法律で定められておらず、将軍をも凌ぐ権勢を誇る者も多かった。管領に就けるのは足利一門の中でも斯波・細川・畠山の三家のみであり、このことから三管領と呼ばれた。 |
| ◆畿内 【きだい・きない】 「畿」は都の意味があるため、都の近郊地五ヶ国の総称として使われる。五ヶ国は五畿内とも言われる、山城(京都)、大和(奈良)、河内(大阪)、和泉(大阪)、摂津(大阪と兵庫の一部)のこと。 |
| ◆キリシタン大名 【きりしたんだいみょう】 キリスト教を信奉した大名のこと。キリシタンの保護、布教の容認、南蛮貿易などを行った。 [ 関連 ] → 大名 |
| ◆近習 【きんじゅう】 主君の側近くに仕える家臣。鎌倉時代に職制として制度化し、室町時代においても将軍の側近くに仕える家臣として存続した。 |
| ◆国替え 【くにがえ】 豊臣秀吉・徳川家康ら天下人が行った、大名の領地を他の地域に移動させること。(=移封・転封) [ 関連 ] → 移封 転封 |
| ◆首実検 【くびじっけん】 戦場で討ち取った首が本物かどうか確かめる儀式。この言葉は首の主が物頭級の時に使われた。 [ 関連 ] → 対面 検知 兜首 平首 |
| ◆蔵入地 【くらいりち】 直轄地。自分の蔵に直接年貢が入る土地という意味。 |
| ◆繰り引き 【くりびき】 撤退時に2つの部隊で行う戦法。 1つの部隊が追撃する敵部隊と戦い、その間にもう1つの部隊が引き、ある程度引いた所で体勢を整える。 そして今度は先に戦っていた部隊が引き、後方で整えていた部隊が敵を受け持つ。 これを繰り返して徐々に引いていく戦法。 |
| ◆郡代 【ぐんだい】 守護大名や戦国大名から、一国のうち一郡もしくは数郡の支配を任された者。 [ 関連 ] → 守護大名 戦国大名 |
| ◆軍忠状 【ぐんちゅうじょう】 戦場における自分や従者などの軍功や死傷状況を大将に上申する報告書。 承認を得た後、返却されて後日の論功行賞の証拠となった。 |
| ◆軍配 【ぐんばい】 軍隊の配置・進退などの指揮を行うこと。 [ 関連 ] → 軍配者 |
| ◆軍配団扇 【ぐんばいうちわ】 軍配者が持つ団扇。鉄や皮に漆を塗り、表裏に、日・月・九曜星・二十八宿・十干十二支などを描き、軍隊の配置・方角などを占った。 [ 関連 ] → 軍配 軍配者 |
| ◆軍配者 【ぐんばいしゃ】 軍の指揮統率をする大将や武将のこと。 [ 関連 ] → 軍配 |
| ◆下剋上 【げこくじょう】 身分の低い者が身分の高い者に勝つこと。 「剋」の字は、訓読みで「かつ」と読み、漢文で「下、上に剋(か)つ」と読む。 |
| ◆化粧料 【けしょうりょう】 女子が受けた財産分与の名義。嫁入り時にこの名義で水田(化粧田)や持参金を持たされたことに由来する。 |
| ◆検知 【けんち】 戦場で討ち取った首が本物かどうか確かめる儀式。この言葉は首の主が足軽級の時に使われた。 [ 関連 ] → 対面 首実検 兜首 平首 |
| ◆減封 【げんぽう】 処罰の一種。領主の領地を減らすこと。 |
| ◆公儀 【こうぎ】 時代により政府・朝廷・幕府などを指すことがあるが、戦国時代においては公的権力という意味で、自分の正当性を主張するために自らが公儀であると言ったりした。 |
| ◆五畿内 【ごきない】 山城・大和・摂津・河内・和泉の五ヵ国を指す。古代より日本の中心区域として重要視された。 |
| ◆国人 【こくじん】 「くにうど」とも読む。土地と繋がりの強い領主を意味し、国衆ともいう。 |
| ◆石高 【こくだか】 田畑の生産力によって定められた土地の価値。年貢の割り当てなどに影響した。 [ 関連 ] → 年貢 貫高 |
| ◆小姓 【こしょう】 主君の近辺に仕える家臣。家臣の子など、少年であることが多かった。 日常生活における雑務から戦時には主君の護衛など様々な役目を負った。 小姓時代に英才教育を受け、後に有力家臣になることも多かった。 |
| ◆後詰 【ごづめ】 先鋒の後ろで交替・補充を行う部隊のこと。または、後で戦場に現れる部隊のこと。 [ 関連 ] → 先鋒 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る