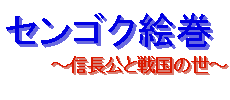
|
| 戦国時代用語辞典 |
|---|
あ か さ た な は ま や ら わ
<< た行 >>
た ち つ て と
| ◆大名 【だいみょう】 地域的な支配権を持つ領主のこと。 語源は、多くの名田を所有する者を大名田堵(だいみょうでんと)と呼んだことからきている。 [ 関連 ] → 守護大名 戦国大名 |
| ◆対面 【たいめん】 戦場で討ち取った首が本物かどうか確かめる儀式。 この言葉は首の主が大将級など高位の者の時に使われた。 [ 関連 ] → 首実検 検知 兜首 平首 |
| ◆武田四天王 【たけだしてんのう】 武田信玄の家臣、馬場信春・山県昌景・高坂昌信・内藤昌豊の呼称。 武田二十四将の中でも最も目立った活躍を見せた部将として選ばれた。 |
| ◆武田二十四将 【たけだにじゅうよんしょう】 武田信玄を支えた24名の武将の呼称。 江戸中期頃から言われた出した呼称で、信玄の時代からあったわけではない。 また、その人選も様々であったが、ここでは次の24名を挙げておくことにする。 武田信繁・武田信廉・穴山信君・板垣信方・甘利虎泰・馬場信春・山県昌景・高坂昌信・内藤昌豊・一条信竜・飯富虎昌・真田幸隆・土屋昌次・小山田信茂・秋山信友・原虎胤・真田信綱・小幡虎盛・原昌胤・多田満頼・横田高松・小幡昌盛・三枝守友・山本晴幸 |
| ◆力攻め 【ちからぜめ】 策を弄せず、我武者羅に攻める攻め方。(=平攻め) [ 関連 ] → 平攻め |
| ◆嫡子 【ちゃくし】 正室から生まれ、家督を継ぐ子のこと。一般的に男が嫡子となることが多いため嫡男ともいわれる。 [ 関連 ] → 庶子 猶子 |
| ◆茶坊主 【ちゃぼうず】 主君の側近くにあり、日常の雑務にあたった僧形の家臣。禅宗の僧侶が雇われたが、後に利発な少年が選ばれるようになった。 [ 関連 ] → |
| ◆使番 【つかいばん】 伝令役。陣中の巡回・視察も行った。 |
| ◆付家老 【つけがろう】 大名本家から分家などに、監督・指導を目的として付けられる家老のこと。 |
| ◆剃髪 【ていはつ】 仏門に入って、髪を剃り落とすこと。(≒出家・入道) [ 関連 ] → 出家 入道 |
| ◆天下 【てんか】 本来は全世界をさすが、戦国時代においては国または日本という意味で使われた。 |
| ◆天下一統 【てんかいっとう】 天下を一(いつ)に統べる。天下統一と同意味。豊臣秀吉の全国統一は、こう称された。 |
| ◆天下人 【てんかびと】 天下を統治する人。本来は天皇や将軍を指すが、織田信長や豊臣秀吉が権力を握ると、彼らを天下人と称した。 |
| ◆天下布武 【てんかふぶ】 天下に武を布(し)く。織田信長が印判などに使用した言葉。日本一国を武力により統一するという意味。 |
| ◆転封 【てんぽう】 豊臣秀吉・徳川家康ら天下人が行った、大名の領地を他の地域に移動させること。(=移封・国替え) [ 関連 ] → 移封 国替え |
| ◆田畠薙ぎ 【でんばくなぎ】 敵地の田畑の作物を刈り取ったり焼き払ったりして、兵糧にダメージを与えること。 |
| ◆東国 【とうごく】 三河−信濃−越後以東の国のこと。 [ 関連 ] → 西国 |
| ◆当世具足 【とうせいぐそく】 南蛮具足の影響を受け、戦国期に流行した質素で実用的な甲冑。鉄砲玉も防げるように鉄板を閉じ合わせて作られた。 |
ホームに戻る ↑ページTOPに戻る