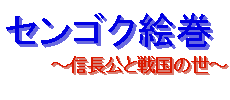
|
| 夢幻の如く…本能寺の変 |
|---|
天正10年(1582年)6月2日、戦国の世を揺るがす大事件が起きた。 京の本能寺にて、織田信長が重臣の明智光秀の謀反に合い、死亡したのである。 後にいう、「本能寺の変」である。 方面軍制により織田軍主力が各地に散った隙をついた謀反。 しかし、光秀は信長殺害より僅か12日後に羽柴秀吉により山崎の合戦に破れ、討たれてしまった。 あまりにもあっけない光秀の最後・・・・・・。 そして、天下の情勢は大きく変わることとなった。 しかし、これだけ大きな事件であるにも関わらず、その全容には未だに多くの謎が残されている。 ここでは、できるだけ変の全容とその背景にあったものに迫ってみたいと思う。 |
|
◆ 天正10年の織田家 畿内を平定した織田家は、天下布武の実現のため、各地に攻勢に出ていた。 北陸では対上杉に、柴田勝家。 中国では対毛利に、羽柴秀吉。 四国では対長宗我部に、織田信孝・丹羽長秀。 関東では北条との調整に、滝川一益。(北条からは織田の分国としての関東一括統治願いが出ていた) しかも、全方面が優勢に進んでいた。 また、東北の伊達や九州の大友や龍造寺も恭順の構えを見せていた。 さらに、この年の4月に、朝廷より三職推任が伝えられていた。 このときの光秀の役目は、畿内の治安維持。 これより中国の秀吉の援軍に向かうように、信長から申し付けられたところだった。 光秀がこの命に従っていれば、中国地方の山陽道から秀吉、山陰道から光秀が治める。 そして、四国を信孝・長秀が治めれば、九州は大友・龍造寺と共に対島津へ。 北陸も弱体化した上杉は敵ではなく、その後は伊達と共に東北平定。 関東も北条との調整が順調にいけば治まったも同然。 まさに、天下統一への道が開けている状態であった。 |
|
◆ 本能寺の変直前の出来事 ◇天正10年4月21日 甲斐・武田氏を討伐し、信長は安土城に帰還。 |
|
◇5月15日 徳川家康と武田旧臣・穴山梅雪が安土へ到着。 信長としては、家康の長年の功績を報いる接待のための招待。 家康としては新たに駿河を与えられたこと、また梅雪は甲斐国の旧領安堵のお礼の訪問であった。 この饗応役を光秀が勤めた。 |
|
◇5月17日 備中高松城を攻めていた秀吉から救援を求める急使が来る。 毛利輝元が援軍を率いて来ることを受けての援軍要請であった。 信長は光秀の饗応役を解任。秀吉の援軍に向かうよう命じ、光秀は坂本城に帰る。 |
|
◇5月19日 信長は、安土城下の惣見寺で幸若大夫の舞いを見て、上機嫌。 |
|
◇5月20日 信長は、家康の接待で幸若大夫の舞いと梅若太夫の能を見る。 始め2回行われた舞いでは上機嫌だったが、能で不機嫌に。最後に、機嫌直しにもう一度舞いを見る。 |
|
◇5月21日 織田信忠が上京し、妙覚寺に入る。 また、家康も接待を受けるなか、京見物のために上京。 |
|
◇5月26日 光秀が丹波亀山城に入る。 |
|
◇5月27日 光秀は、戦勝祈願のために愛宕山に登る。 神社に参籠して、くじを2・3度ひく。 |
|
◇5月28日 光秀は、里村紹巴らの連歌会に出席。 発句は光秀より「時は今あめが下しる五月哉」。 「時」は光秀の出自の「土岐氏」。「あめが下しる」は「天下を統治する」という意味に解釈され、光秀の野望を表すといわれる。 または、「時は今」を三国志の故事より「危急存亡の時」。「あめが下しる」は「天が下界のすべてを見ている」とし、この国を憂いた結果の決意を表すともいわれる。 |
|
◇5月29日 信長が上京し、本能寺に入る。 従えたのは近習2・30人と、少数の者達。(100名程度?) |
|
◇6月1日 (この年は5月29日の翌日が6月1日) 信長は、近衛前久ら公家衆に入京の祝賀を受け、盛大な茶会を開催。 普段は茶会に数人しか呼ばない信長だが、このときは50名以上が出席したという。 三職推任による信長(もしくは信忠)政権誕生の公家に対する仕上げだったのかもしれない。 夜には、信忠と村井貞勝らとともに歓談。その後、信忠らは妙覚寺へ帰る。 また、家康と梅雪は堺見物の後、松井友閑の元に滞在。 一方、光秀は亀山城から京に向けて出陣。その数は1万3千ほど。 |
|
◆ 本能寺の変 ◇6月2日 ◎太田牛一「信長公記」より 明け方、光秀率いる軍勢が本能寺を取り囲み、四方から乱入してきた。 信長も小姓衆も初めは下々の者がけんかでもしているかと思ったが、敵がときの声を上げて鉄砲を撃ちかけてきたため、敵襲と知った。 信長が「さては謀反か、いかなる者のしわざか」と尋ねると、森蘭丸が「明智の手のものと者と思われます」と言ったので、信長は「是非もなし」と覚悟を決めた。 信長は、はじめ弓をもって数回射たが、しばらくすると弓の弦がきれたので、今度は槍をもって戦った。 しかし、肘に槍傷を受けたため、館の奥に引きあげる。 女中衆が付き添いを申し出たが、信長は「女たちは急いで脱出せよ」と指示した。 信長は火のひろがった御殿奥深くに入り、納戸を閉め、自害した。 ◎「イエズス会日本年報」より 明智の兵は戸から、さしたる抵抗も受けず、すぐに中に入った。 信長はあたかも起床して、その顔や手を洗滌し、これを拭いつつあった。 そこへ兵が矢を放ち、その肋骨に当たった。 彼はそれを抜き、薙刀をふるって戦ったが、腕に弾創を受けて、室に入り戸を閉じた。 あるものは切腹したと言い、あるものは火を放って焼け死んだとも言う。 ともあれ我々が知り得たのは、その声だけでなくその名を聞いただけで戦慄した人が、毛髪も残らず塵と灰に帰したことである。 ◎「日本王国記」より 死に際して信長は「余は余自ら死を招いたな」と言った。 ◎「寛永十七年本城惣右衛門自筆覚書」より (以下、光秀軍に従軍していた惣右衛門の書) 夜明け前に桂川を渡って京都に入る直前に、本能寺の敵を急襲することが全軍に伝えられた。 本能寺というところは知らず、相手が信長様とは夢にも思わなかった。 その頃、家康様が上洛していたので、家康様を襲うものと思った。 本能寺への討ち入りは、北門から重臣・斉藤利三の子息が、惣右衛門らは南門から侵入した。 討ち入って首を1つ挙げたところ、明智秀満の幌衆から首は打ち捨てと言われた。 殿舎の広間に来ても人がいなかった。 逃げてきた白装束姿の女を捕らえたところ、上様は白い着物を召していますと言われたが、 その上様というのが信長様のことを指していたのはわからなかった。 上で紹介したものをまとめると、どうやら本能寺にはほとんど兵はおらず、 信長は夜着姿の時に襲撃され、あっという間に敗れたということになる。 しかし、その死体は見つからなかったようだ。 一方、妙覚寺にいた信忠は、村井貞勝から変の報告を受け、より防備の厚い二条御所へ移った。 信忠らは下の御所と呼ばれる場所に入り、同御所にいた誠仁親王らを上の御所に移す間をもらうことを包囲している光秀に伝えて快諾を得る。 午前8時頃にその移動が終わり、光秀軍の攻撃が開始された。 信忠軍は1500騎ほどしかおらず、衆寡敵せず、火もかけられて、信忠は自害した。 |
|
◆ 本能寺の変直後の出来事 ◇6月2日(変の直後) 光秀は、変で混乱する京を制圧。 安土城を抑えるため、近江に進軍を開始する。 堺を遊覧中に変を知った家康は、伊賀の山道を越えて、伊勢から三河へ帰還。 |
|
◇6月3日 秀吉が使者より変の勃発を知る。 その使者は長谷川宗仁の手の者とも、光秀が毛利氏に向けて送った密偵を捕まえたともいわれる。 |
|
◇6月4日 光秀が安土に到着。 安土では留守役の蒲生賢秀が信長妻女達を連れて退去したあとで、抵抗は僅かであった。 一方、秀吉は毛利氏と講和し、大返しの準備にかかる。 また、四国へ渡る間際だった信孝・長秀も、変の報を受けて混乱する軍をまとめようとしていた。 |
|
◇6月5日 光秀は、元々が西近江を領土としていたため、なんとか近江を制圧することに成功。 信孝・長秀が、信長の甥だが光秀の娘婿でもあった津田信澄を殺害。 毛利氏が変の勃発を知るが、秀吉との講和を重視して、静観。 |
|
◇6月6日 秀吉が沼まで進軍。 |
|
◇6月7日 光秀は朝廷より覇権の認知を受ける。 秀吉が姫路まで進軍するが、光秀はこれに気付かず。 |
|
◇6月8日 光秀は、摂津・河内方面に軍を進める。 美濃方面では、光秀に呼応した安藤守就が稲葉一鉄に討たれる。 |
|
◇6月9日 光秀は、京により朝廷に献金し、京の治安を任される。 しかし、長年親交のあった丹後の細川藤孝・忠興父子が協力を拒否。(忠興は光秀の娘婿) |
|
◇6月10日 河内に入った光秀に、秀吉が近日のうちに進軍してくるとの報が入る。 これにより、光秀になびきつつあった勢力が離散。大和の筒井順慶も撤退。 |
|
◇6月11日 光秀は、順慶に再び使者を出すが、使者は順慶により殺害。 秀吉が尼崎まで進軍。 |
|
◇6月12日 秀吉は、池田恒興・中川清秀・高山右近ら摂津衆を吸収し、勢力を拡大。 信孝・長秀の到着を待ったが、秀吉に主導権を取られたく信孝は警戒の姿勢。 光秀は、紀伊雑賀に協力要請。 さらに、家康が安土まで進軍してきたとの虚報が流れたが、この時の家康は まだ尾張にもついていなかった。 |
|
◇6月13日 山崎の戦い 信孝が順慶に書状を送り、参陣を要求。 正午頃、信孝自身も秀吉と合流。 16時頃、戦端が開かれ、僅か2時間ほどで光秀は惨敗。 夜になり、坂本に落ちのびる最中に落ち武者狩りにあったという。(定説) 光秀の首は、秀吉の命で、本能寺跡に晒された。 このとき、家康は尾張熱田にて光秀討伐の報を受け、引き返した。 柴田勝家は、北陸でまったく身動き取れず。 滝川一益は、北条の攻撃を受け、撤退。 また、安土城は光秀の死後、謎の発火により消失した。 |
|
◆ 信長の死因・死体の行方 本能寺の変後、明智軍は信長の死体を探したが、見つからなかった。 信長の死体はどうなったのだろうか。 また、どういう死に様だったのでしょうか。 まず有名なものは、割腹死説・焼死説があります。 これらは、信長公記やイエズス会の報告書にあります。 また、信長の墓所としてもっとも早く作られたとされる阿弥陀寺の記録では、変を知った住職がまだ争っている最中に裏口から 本能寺に入ると、信長の家臣達が遺骸を火葬していたので、密かに遺骨を引き取ってきたとある。しかし、これはどう考えても嘘くさすぎます。 面白いものでは、変の一年半後に日本人宣教師が出した報告書で、信長は少しも準備がなかったので防ぐことはできず、小銃で撃たれて殺されたというものもあります。 また、爆死説もあります。 信長は出陣のときは常に火薬の大甕を担がせて、もしものときはこれで死体を吹っ飛ばしてしまうと言っていたというもの。 本能寺は寺とはいえ要塞であり、火薬庫なども存在しており、そこに引火して爆発したというもの。 さらには、信長を殺したのは実はキリスト教徒で、本能寺のすぐそばにあった南蛮寺の展望台から新型火薬爆弾を打ち込んで焼失させたというものまであります。 このことに関しては、どれも信憑性はなく一切不明です。 なので、私的に想像で言わせてもらうと、一瞬にして敗れたのに死体が見つからなかった という点から、爆死だと思います。 ただし、信長1人を爆発させる程度の火薬量での自爆だと思います。 首を取られるのは恥じになるので、割腹してから火葬させるというのは危ういし、 時間もなかったと思います。 それなら、一瞬の爆発による消失のほうが、信長のイメージにも合う気がします。 松永久秀など自爆死の先例もありますし、ありえないことではないと思いますが、どうでしょうか。 |
|
◆ 本能寺の変の裏事情 光秀が本能寺の変を起こした理由については不明点ばかりで、様々な説が言われている。 ここでは、それらの説を紹介・考察したいと思う。 ≪ 光秀 単独説 ≫ 信長に対する恨み ・丹波八上城攻めにおいて、光秀は自分の老母を人質に出して八上城主の波多野兄弟を誘い出したが、 信長が彼らを殺したため、報復に老母も殺された。『総見記』『常山紀談』 ・甲斐武田攻めの後に、信長に「おのれに何の功があったか」と折檻された。『川角太閤記』 ・信長が光秀の妻に手を出そうとして断られたことを恨んで、光秀を冷遇したため。『落穂雑談一言集』 ・家康の饗応役を精魂こめてまっとうしようとしたが、信長に気に入られず免職。 さらに、急に中国攻めの援軍に行くよう言われた。『甫庵太閤記』『川角太閤記』 天下への野望 ・光秀の過度の利欲と野心が募り、ついにはそれが天下の主になることを彼に望ませた。 『フロイス日本史』 焦り ・中国攻めに際し、信長から現在の領地を取り上げられ、これから攻め入る先を領地に当てられた。 ・中国攻めの大将が秀吉であり、その下風に立たされた敗北感。 ・光秀が四国の長宗我部に対する申次役を務めていたが、領地をめぐって関係が悪化し、 長宗我部攻めに信孝らが出陣するまでになった。 ・重臣・斉藤利三を稲葉一鉄に返すよう信長から命じられたが、光秀が拒否し、関係が悪化した。 (斉藤利三はかつて稲葉一鉄の家臣だった) ・森蘭丸が亡父・可成の旧領である近江志賀郡の所領を望み、信長がそれに応じる構えだった。 (近江志賀郡は光秀の領地) 正義感 ・比叡山焼き討ちなど、信長の残虐性を見かねて。 ・朝廷を無視するなど、信長の国体を無視した行動を見かねて。 <考察> 恨みや正義感の項目は、物語や伝聞によるものが多く信憑性は薄い。 野望や焦りというのはあったかもしれないが、結局は光秀の心情であり、 想像の域を出るものではないと思う。 この単独説が本当ならば、光秀の先見性に疑問を持たざるを得ない。 中央で孤立して滅びた結果を考えると、「焦り」による凶行だったのだろうか。 ≪ 朝廷 共謀説 ≫ 暦の改訂や正親町天皇の退位を迫る信長を危険視し、 朝廷が懇意にある光秀に信長殺害を命じたという説。 特に光秀よりの動きを見せている近衛前久の策動が大きいとも。 <考察> 上の時系列を見て、本能寺の変から朝廷が光秀の覇権を認知するまでの期間は「5日」。 その間、光秀は金を京や近江でばらまき、必死に人気取りを図っている。 この対応の遅さを見るに、朝廷が黒幕とはいえないと思う。 朝廷から信長打倒の命があったなら、光秀は公然と信長を包囲・処刑できたはずだ。 また、朝廷から諸大名に働きかけてもらい、混乱をまとめることもできたと思われる。 既に力のなかった朝廷には、信長に対抗する気もなく、変わって光秀が京を占領すると、 それにも従わざるを得なかった。 そこで、迷った末に、覇権の認知をした・・・と、これが真実と思われる。 よって、この説には無理があるように思う。 しかし、覇権認知の日に御所に祝い酒を進上している近衛前久は黒かもしれない。 ≪ 足利義昭 共謀説 ≫ 信長に追放された義昭が、旧臣の光秀に命じたという説。 <考察> 光秀の配下には、伊勢貞興や蜷川貞周ら義昭の旧臣が多くいたが、 光秀と義昭の関係は、義昭追放前からとっくに切れていると思われる。 また、変時に義昭は毛利輝元の庇護化にあり、輝元の支援を受けて上洛を狙ったが、 親秀吉派の反対で実現しなかった。 また、他の諸大名にも書状を送っているが、実現しなかった。 もし義昭が共謀したとすれば、このような後手に回ることはなかったはずだ。 また、義昭はこの時点でまだ将軍職を辞しておらず、義昭の命で光秀が動いたとすれば、 光秀は将軍の命で行ったと公言できたはずです。 よって、この説も無理があるように思う。 ≪ 斉藤利三 共謀説 ≫ 長宗我部元親に妹を嫁がせている利三が長宗我部攻めを中止させるために、 主君である光秀をそそのかして変を起こさせたという説。 <考察> 利三の理由としては疑う所もないように思う。 しかし、利三主導だろうと光秀と相談して決めたことだろうと光秀の一軍内のことであり、 光秀単独説のように先見性がないと言わざるを得ない。 しかし、想像の域は出ないが、否定すべき点もないと思われる。 ≪ 羽柴秀吉 共謀説 ≫ 天下を目論む秀吉が、信長を中国への応援を頼むことで誘い出し、光秀に討たせた。 そして、その後、中国大返しを行い光秀を討って口封じをしたという説。 <考察> 確かに、本能寺の変は秀吉が信長を呼んだことに起因するが、疑問点も多い。 疑問1、信長を呼ぶ必要があったのか。 備中高松城攻めを行っていた秀吉軍は3万ほどで、そこへ毛利輝元率いる3万(4万?)の軍勢が迫っていた。 戦力に大差はないように思うが、城攻めをする側は3倍もの兵力がいるとされる。 武田攻めから帰っていた信長に余力があったなら、毛利と決戦を行う好機でもあるため援軍要請は当然か。 この点は、信長がすぐに出兵を決めたことから、両者の間に意見の相違はなかったように思われる。 疑問2、なぜ中国大返しが可能だったのか。 秀吉は賤ヶ岳の戦いでも大返しを実行しているが、この時は事前に補給箇所を設置するなど準備してあったとされる。 では、中国大返し時も、変を知っていたため、事前に準備してあったということだろうか。 この点では怪しいとも思われるが、大返しの道中の大半が自国の播磨であったことを考えると、 道中の補給の手配なども順調にいき、たまたま強行軍がうまくいったとも考えられる。 疑問3、変を知った後、なぜ毛利は秀吉を追撃しなかったのか。 親秀吉派で追撃に反対したのは小早川隆景や安国寺恵瓊。 恵瓊は「信長の世は長く続かず、その後は秀吉が台頭するだろう」と天正元年段階で予言したとされる毛利の外交僧です。 秀吉が変を知っていたとすれば変以前から、この親秀吉派とも共謀していたのだろうか。 疑問4、なぜ秀吉と光秀が共謀したか。 両者の間に共謀するような接点があったとは思えない。 これならば、光秀 単独説に、秀吉の野望が便乗したという方が、まだありえるように思う。 疑問1の解。光秀の思いを知っていた秀吉が信長を誘い出し、光秀が討ちやすい場を与えた。 疑問2の解。事前に準備していたため、大返しが可能だった。 疑問3の解。毛利の親秀吉派と内通し、事前に講和を進めていた。 疑問4の解。光秀と共謀はなく、光秀が独自で動くのを待ち、狙い討った。 しかし、疑問1の解は、信長と出陣に対する意見の相違がなかった点からおかしい。 また、疑問3の解で、毛利の将と内通していたとすると、変が失敗したら秀吉の命運も危ういが、そんな賭けに出たのだろうか。 内通はなく、毛利の動きについては賭けだったのかもしれない。 疑問4の解も、光秀が本当に動くか確証がなく、やはり運頼りでしかない。 よって、やはり秀吉は運がよかったとしか言いようがないと思われる。 疑問1の解。毛利との決戦のため、信長の出陣は必要だった。 疑問2の解1。中央との補給線が確立していたため、運よく大返しが可能だった。 疑問2の解2。光秀の考えを察し、事前に準備していた。 後の秀吉の行動から見て、野心がなかったとは思えない。 もし光秀が事を起こすようなら、大返しできるように準備だけはしておいたのかもしれない。 疑問3の解。毛利氏の内部で意見が分かれ、運よく親秀吉派の意見が通った。 疑問4の解。光秀と共謀はなかった。 ≪ 徳川家康 共謀説 ≫ 信長の命で、正妻・築山殿と嫡男・信康を殺さざるを得なかったことを恨み、光秀と共謀。 光秀は後に天海となり家康に仕えたという説。 <考察> 変後の家康の行動を見てみると、まず堺から伊賀越えをして伊勢から海路で三河に帰っている。 その後、尾張まで出兵するも、山崎の戦いで光秀が討たれたことを知り、引き返す。 そして、混乱する甲斐・信濃に出陣して、これを手にしている。 ここから家康共犯説についても疑問点を挙げていこうと思う。 疑問1、築山殿と信康の件で恨みがあったか。 信長が信忠より優秀な信康を危険視して殺させたという話もあるが、実際はどうだったのか。 信康は武田氏との戦いにおいて数々の功績があったようだが、信忠も劣らず功績を挙げており、特別劣っているようにも見られない。 また、信康の件は、家康が自分につく派と信康につく派とに国内が分裂するのを恐れ、家康の意思によって信康を殺したという説や不仲説もある。 さらに、信長は処罰内容は家康に一任していて殺せとは言っておらず、築山殿については触れていない。 また、その件で信長に謁見した酒井忠次は、大した弁明もしていない。 後に弁明しなかった酒井忠次に対して家康が恨んでいる節を見せる話もあるが、息子を自ら殺したという悪印象を消すためと思われる。 忠次自身も、その後も変わらず重用されている。 築山殿も正室とはいえ今川との同盟の証。織田と結んだ後は、諍いの種でしかない。 疑問2、なぜ光秀と共謀したか。 そもそも家康に信長を殺す動機があったのか。 あったとすれば、このとき信長が家康を上洛させた目的が、家康暗殺にあったという場合だ。 これを知った光秀が家康を協力させようとした・・・。 よって、共謀ではなく、光秀に協力を頼まれたと見る方が自然な流れに思われる。 家康を暗殺する必要があったかという疑問は残るが、元々 徳川との同盟は東国の抑えのためである。 今川・武田家が滅び、北条も傘下に入るとなると、同盟関係である家康の存在感は邪魔かもしれない。 疑問3、伊賀越えは、なぜ可能だったか。 伊賀は信長と敵対関係にあり、前年の9月に平定したばかり。信長に恨みを持つ者が多く、それは同盟者の家康も同様であったと思われる。 服部正成の父・保長が伊賀忍者の頭領であったといわれているが、正成自身は三河出身であり、果たして協力が得られたものか。 だが、前述の信長に暗殺される恐れがあったという点から考えれば、信長から逃げるために事前に協力を要請して準備していれば可能だったかもしれない。 また、穴山梅雪は逃亡中に殺されているが、後に甲斐・信濃を攻めていることから、これが家康の仕業と考えるのは納得できる。 疑問4、光秀=天海? 南光坊天海は、江戸幕府初期の朝廷政策・宗教政策・軍事と幅広く活躍した家康配下の高僧です。 しかしながら、その前半生は謎に包まれており、数々の伝承が残るのみ・・・。 天海が家康に仕え始めたのは、慶長4年(1599年)頃か? 光秀=天海に関する伝承は多い。 ・本徳寺の光秀の位牌に、慶長4年にこの寺を開いたという記載あり。 ・日光東照宮に先駆けて天海が建てた日吉東照宮の場所は、光秀の旧領・坂本。 ・日光東照宮の近くに天海は明智平という地名をつけた。 ・日光東照宮に桔梗の紋。桔梗紋は光秀の家紋。 ・天海に会った徳川家光の乳母・春日局がお久しゅうございますと平伏。 春日局は光秀配下の斉藤利三の娘。また、家光の「家」は家康。「光」は光秀? ・慶長20年(1615年)比叡山の石灯籠に光秀寄贈と書かれたものがある。天海は天台宗。 ・天海の諡号は「慈眼大師」。光秀が建て、光秀を祀る寺に慈眼寺がある。 さて、私的回答としては、家康は黒に近いが灰色という感じでしょうか。 疑問1の解。すべては徳川安泰のため。恨みはなかった。 疑問2の解。共謀もありえなくはない。 保身のために光秀を支持したとは考えられる。 前述の通り、信長にとって徳川は役目をほぼ終えた存在である。 そして、伊賀越え後の西進も光秀につくためかもしれないし、光秀と協力すれば旧織田勢を排除して、天下に近づいた可能性はある。 疑問3の解。地元に協力者がいたので可能だった。 元より家康自身が命を狙われていたのではなく、巻き込まれ防止である。 服部正成自身はともかく、その親類等の伊賀衆の協力が得られれば可能である。 疑問4の解。光秀≠天海。 光秀=天海を示す項目に、伝承や物語が多く、証拠がない。 (光秀生存説については、本能寺の変とは関係ないので、ここでは考えません。) 天海は天台宗の高僧なので、比叡山を焼き払った信長を敵視しており、信長を倒した光秀に尊敬の念を抱いていた。 こう考えることで説明できる。 天海については、陸奥国生まれの芦名の一族。天台宗を学ぶも比叡山焼き討ちから武田信玄の保護下に入り、後に無量寿寺北院へ行って天海と号したという話がある。 よって、光秀=天海は、物語としては面白いが創作だと思います。 |
戻る